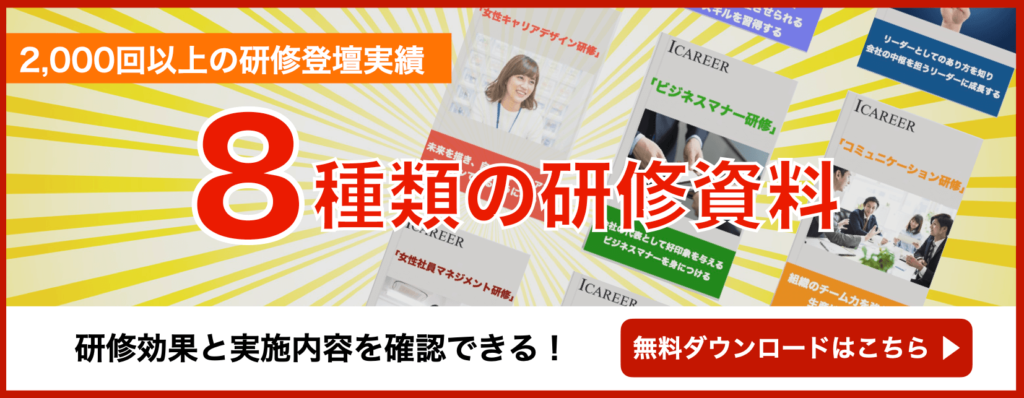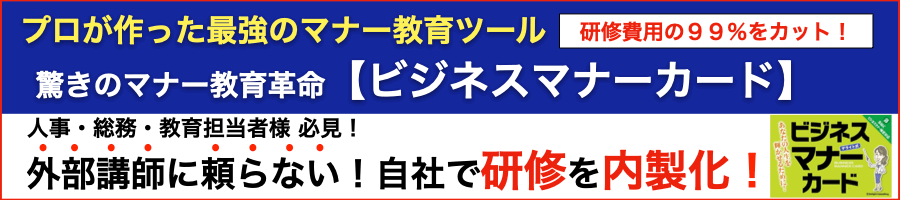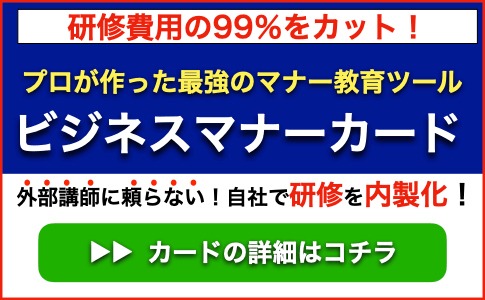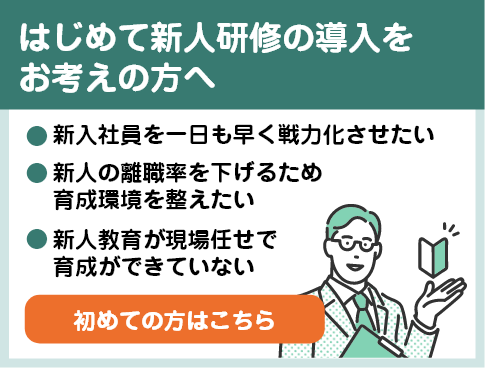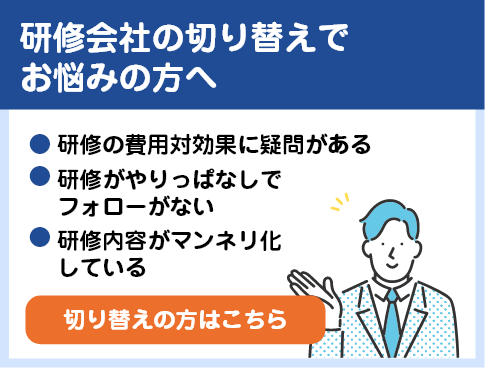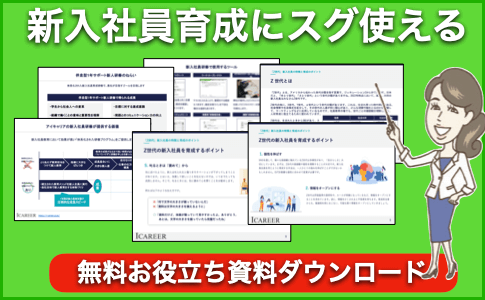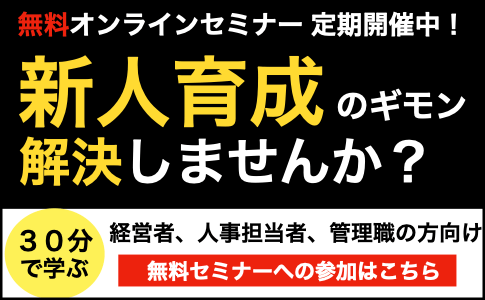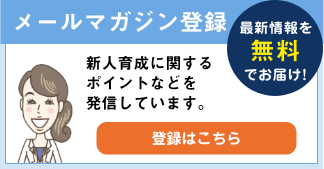五月病?やる気が出ないときの対処法
2021年05月22日 2024年08月26日 ビジネスコミュニケーション

ゴールデンウィークの大型連休が過ぎた頃に、やる気が出ない、体がだるい、集中力が続かないといった症状が出ることがあります。それはいわゆる『五月病』かもしれません。
研修講師として、社会人が健全に働くために必要な五月病の対処法を知っていただきたいと思っています。これよりは、厚生労働省が出している文章等を元に分かりやすくお伝えします。
YouTube版も公開しています
動画でも学べます。聞き流すだけでも理解できますよ!
五月病とは
4月は新入社員が社会人になり、中堅・ベテランも部署異動、転勤などで新しい環境で働く人が増える時期です。人間関係や仕事内容がガラリと変わる中、頑張り過ぎて知らないうちにストレスを溜めている人が多いものです。そんな中、ゴールデンウィークの大型連休を取ったあとに、一気に疲労感が出て心身の不調が生じるのが五月病です。
五月病は正式な病名ではありません。医学的には「適応障害」「軽度のうつ」などの病気と関係があるとされています。
五月病チェック
五月病の症状としては以下の特徴が挙げられますので、チェックしてみましょう。
上記の自覚症状がある方は、早めの対処をおすすめします。
大型連休明けに新入社員研修に登壇すると、『睡眠がしっかり取れない日が続いています』などの声を聞きます。研修担当者にそれを報告すると知らない事が多いものです。特に新入社員は体調が悪くても、言い出しづらいのではないかと察します。ゴールデンウィーク明けは、新人の周りにいる上司・先輩が注意深く観察する必要があります。
自分のストレス対処法を知っておく
五月病の対応策は、症状が悪化する前にストレスを解消していくことです。まずは、自分の心身の変化に気づいて『セルフケア』をしていきましょう。
あなたは何をするとスキッとしますか。人それぞれストレスの発散方法はありますので、自分に合ったストレス対処法を知っておきましょう。
□友人と話す □とにかく寝る □カラオケで歌う □甘い物を食べる □スポーツをする □ゲームをする □愛犬と遊ぶ □散歩をする など 研修で出た少数意見として『包丁を研ぐ』という人もいました。「夜、暗いところで研がないでね」とお伝えしました(笑)
仕事から離れて好きなことに没頭できると、ストレス解消になります。休日に意識してストレス解消をすることにより、仕事への意欲を高めます。
自分の「考え方のクセ」に気づいて改善しよう
以下にあてはまっている人は、自分で自分を追い込んでしまっているかもしれません。自分の考え方に良くないクセがないかチェックしてみましょう。
□すべき思考、ねばならない思考
「失敗するべきでない」「最後までやり遂げなければならない」等の融通が利かない考え方を持っている。思いどおりにならない相手に腹を立ててしまいます。⇒否定的に断定をしないようにする。
□全か無か思考(完璧主義)
物事を見るときに、「○か×か」「白か黒か」「良いか悪いか」という両極端な見方をしてしまう考え方です。⇒「できなかったこと」ではなく、「できていること」に目を向ける。自分にも相手にもグレーゾーンをつくる。
□一般化のしすぎ
自分の意見を数人に批判されただけで、「いつも私の意見を批判する」 「いつもこうだ」と一般化してしまうクセのことです。⇒本当は、いつもではないかもしれません。本当に毎回そうだろうかと問い直してみましょう。 研修で見る限り「考え方のクセ」が多いと、疲れている傾向にあります。固定観念に縛られず、柔軟な考え方ができるといいですね。難しいかもしれませんが、もっと気楽に過ごしてもいいのではないでしょうか。まずは自分を一番大切にしてください。
まとめ
五月病になる人は、まじめで頑張り屋さんが多いものです。仕事も大事ですが、あなたの体が一番大事です。心身の不調が出ている方は、遠慮なく周りの人に相談して休んでください。
「迷惑がかかるから休めない」と思っている方。無理して仕事を続けて長期離脱や退職という事になった場合、余計に迷惑がかかってしまいます。まだそこまで不調は出ていないが、疲れがとれないという方は悪化する前にセルフケアをしてみてください。
人生100年時代。まだまだ先は長いですので、長く働き続けるためにも自分の体は自分で守っていきましょう。
執筆者プロフィール
 新人育成トレーナー
新人育成トレーナー
アイキャリア株式会社太田 章代- 企業・団体でのコミュニケーション研修、ビジネスマナー研修など、2,000回以上(2023年現在)登壇。 プロフィール詳細
新着記事
-
-
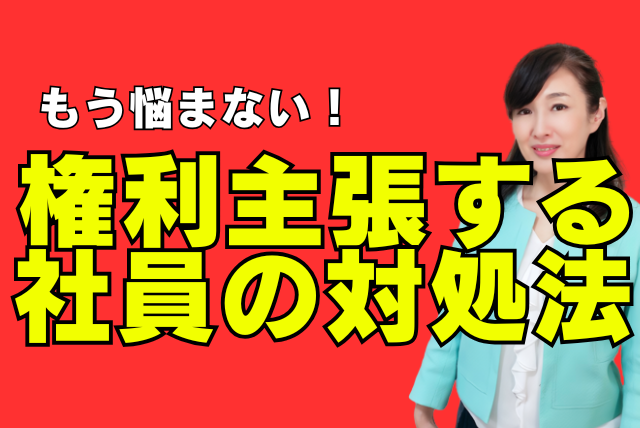
- 【管理職向け】権利ばかり主張する若手社員への正しい対処法|「義務を果たせ」と叱る前にやるべきこと 2025年07月07日
-
-
-
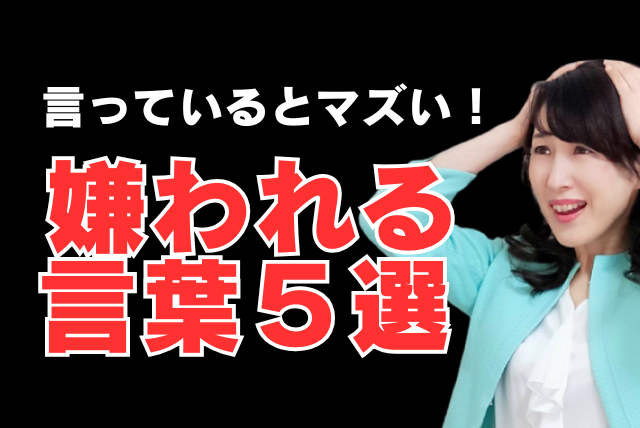
- 職場で「嫌われる人」の特徴とNGフレーズ5選 2025年04月17日
-
-
-
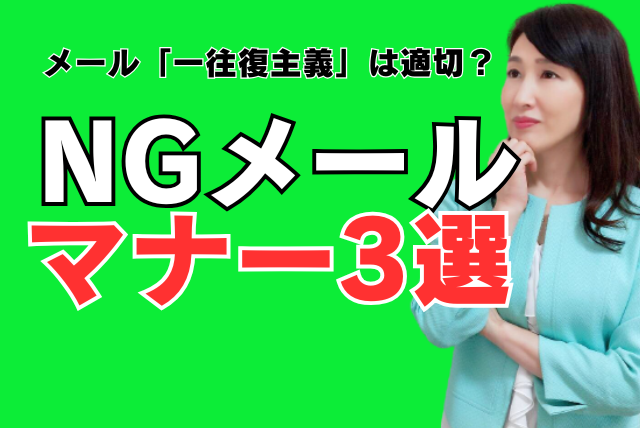
- 近年のNGメールマナー3選|メール1往復主義はありか【若手社員必見!】 2025年04月11日
-
カテゴリー