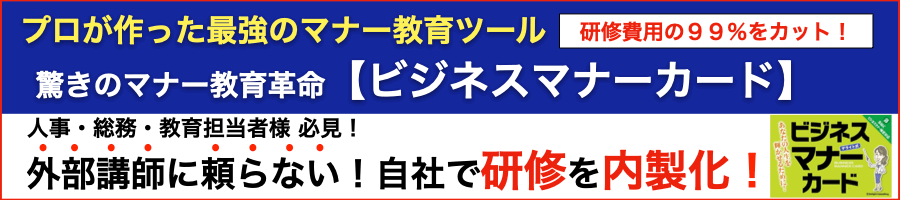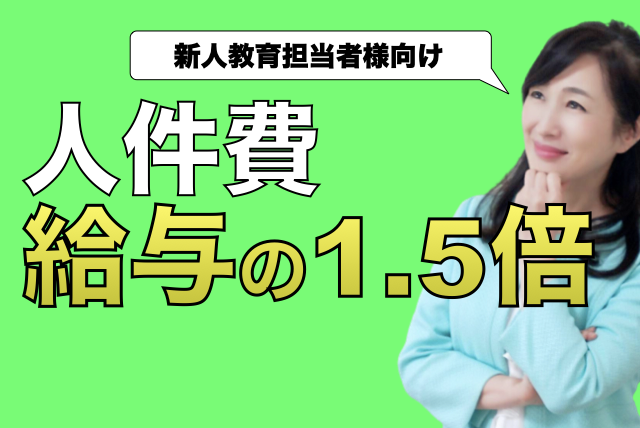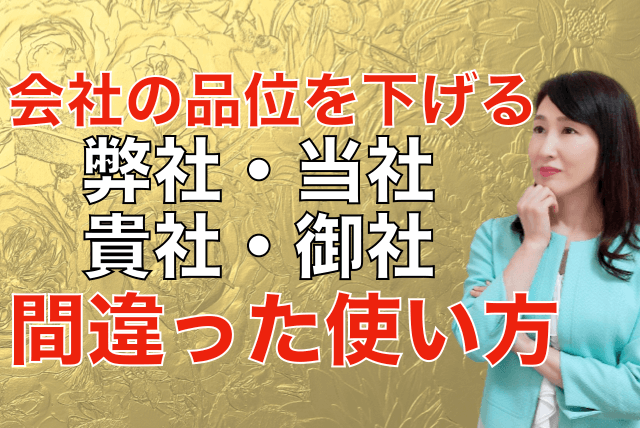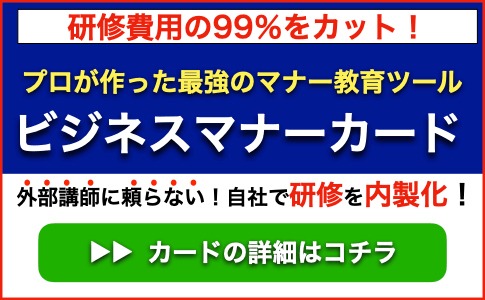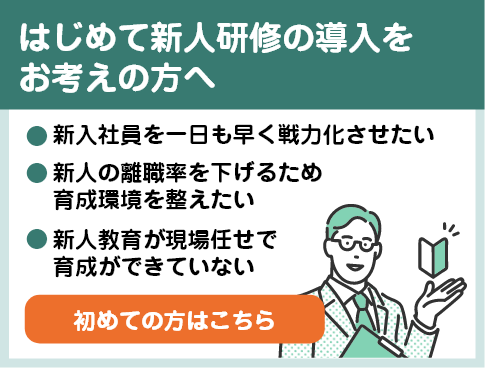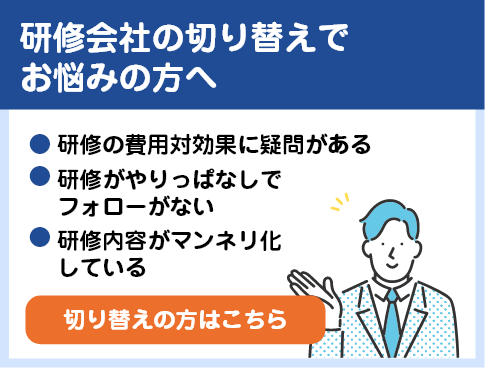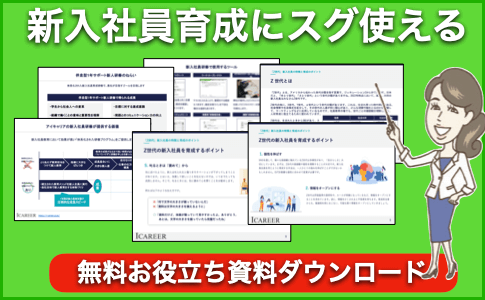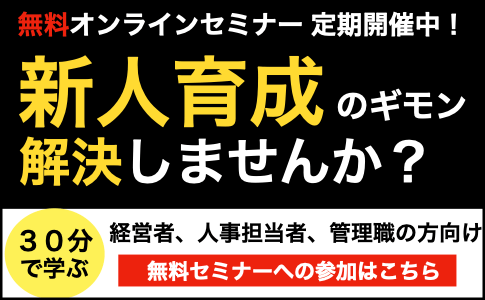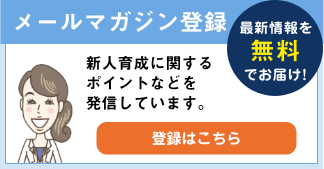部下を急成長させる『社会人の基礎力』
2025年07月26日 2025年07月29日 新人育成担当者向け、ビジネスコミュニケーション
こんにちは。人材育成トレーナーの太田章代です。
私が企業研修で登壇した際に、管理職の方から以下のようなお話を伺います。
「部下が指示待ちで、なかなか主体的に動いてくれない」
「主体性の重要性はわかるが、どう指導すればいいのかわからない」
管理職のお悩みに出てくるワード「主体性」は、経済産業省が提唱する「社会人基礎力」の重要な要素の一つです。多くの人がその大切さを理解していながら、具体的な育成方法がわからずにいるのが現状です。
そこで今回は、人材育成に悩む教育担当者の皆さまに向けて、社会人の土台となる「社会人基礎力」の全体像と、その中でも特に重要な「主体性」を部下に身につけてもらうための具体的な方法を解説します。
YouTube版も公開しています動画でも学べます。聞き流すだけでも理解できますよ!
社会人としての土台を作る「社会人基礎力」とは?
「社会人基礎力」とは、経済産業省が「人生100年時代の社会人基礎力」として提唱している、これからの時代を生き抜くために必要な能力のことです。
これは、パソコンに例えると分かりやすいかもしれません。
- OS(思考・価値観):社会人基礎力、キャリア意識、マインドなど、個人の土台となる部分。
- アプリ(スキル・能力):専門知識や社内特有のスキルなど、業界や職種に応じた能力。
どれだけ高性能なアプリ(専門スキル)を持っていても、土台となるOS(社会人基礎力)が脆弱では、その能力を十分に発揮することはできません。例えば、スキルは高いのに主体性がなく言われたことしかしない、あるいはチームで協力する意識が低い、といったケースです。
社会人基礎力は、キャリアの初期段階、特に新入社員や若手社員のうちにしっかりと身につけておくべき土台なのです。
社会人基礎力を構成する「3つの能力」と「12の能力要素」
社会人基礎力は、大きく分けて「3つの能力」と、それをさらに細分化した「12の能力要素」で定義されています。これらはすべて、意識して教育することで誰もが伸ばせる能力です。
1. 前に踏み出す力(アクション)
〜失敗を恐れず、一歩前に踏み出し、粘り強く取り組む力〜
- 主体性:物事に進んで取り組む力。指示待ちではなく、自らの意思で考えて行動します。
- 働きかけ力:他者に働きかけ、巻き込む力。周囲と信頼関係を築き、協力を引き出します。
- 実行力:目的を設定し、確実に行動する力。計画を立て、最後までやり遂げます。
2. 考え抜く力(シンキング)
〜現状を分析し、目的や課題を明らかにして解決策を考える力〜
- 課題発見力:「なぜ?」を繰り返し、現状を分析して本質的な課題を明らかにする力です。
- 計画力:課題解決までのプロセスを設計し、準備する力。ゴールから逆算し、優先順位をつけて行動計画を立てます。
- 創造力:新しい価値を生み出す力。既成概念にとらわれず、新たなアイデアを発想します。
3. チームで働く力(チームワーク)
〜多様な人々とともに、目標に向けて協力する力〜
- 発信力:自分の意見を分かりやすく伝える力。相手に伝わるように工夫し、行動を促します。
- 傾聴力:相手の意見を丁寧に聴き、真意を理解しようと努める力です。
- 柔軟性:意見の違いや立場の違いを理解し、臨機応変に対応する力です。
- 状況把握力:自分と周囲との関係性や、物事の全体像を正しく理解する力です。
- 規律性:社会のルールや人との約束を守る力。時間や納期、コンプライアンスの遵守などが含まれます。
- ストレスコントロール力:ストレスの発生源に対応する力。近年では、困難な状況から回復する力「レジリエンス」とも呼ばれています。
これらの能力を発揮するには、まず自分自身の強み・弱みを客観的に把握し、「何を学び、どう活躍したいのか」を考えることがキャリアを切り拓く上で不可欠です。
【実践編】部下の「主体性」を育てる4つのステップ
では、これらの基礎力を部下にどう教育すればよいのでしょうか。今回は、冒頭の課題でもあった「主体性」を例に、具体的な育成ステップをご紹介します。「主体性を身につけなさい」とただ言うだけでは、人は変われません。
1. 目的を伝える
「なぜ主体性が必要なのか」を、会社のビジョンやチームの目標と結びつけて具体的に説明します。目的が明確になることで、部下は納得感を持って行動できます。
2. 具体的な行動に落とし込む
「主体性」という抽象的な言葉を、実際の業務に即して具体化します。「例えば、今ある営業資料だけでなく、お客様がもっと喜ぶような資料を自分で考えて作ってみよう」というように、行動レベルで伝えます。
3. 小さな成功体験を積ませる
実践の機会がなければ、主体性は育ちません。まずは小さな仕事から任せてみて、主体的にやり遂げる経験を積ませる環境を作りましょう。
4. 前向きなフィードバックをする
主体的に動いた結果を、強みと弱みの両面からフィードバックします。たとえ失敗したとしても、それは成長の機会です。改善点を伝え、次への挑戦を促す前向きな声かけを心がけましょう。
要注意!部下の主体性を奪うNGな関わり方
良かれと思ってやっていることが、実は部下の主体性を奪っているかもしれません。以下の点に心当たりはないか、チェックしてみてください。
何でも教えすぎていませんか?
先回りして答えを教えると、部下が自ら考える機会を奪ってしまいます。
失敗を許容できていますか?
主体的な挑戦に失敗はつきものです。失敗を過度に恐れる環境では、誰も挑戦しなくなります。
マイクロマネジメントをしていませんか?
業務の進め方を細かく指示しすぎると、部下は「言われた通りにやればいい」と考え、主体性を失います。
【最重要】会社の方向性やビジョンを伝えていますか?
部下がどれだけ主体的に動きたくても、進むべき方向が分からなければ動けません。
判断の軸となるビジョンや目標を日頃から明確に伝えることが、上司の最も重要な役割です。
まとめ
今回は、社会人に必要な「社会人基礎力」と、その一つである「主体性」の育て方について解説しました。
1. 自社で特に必要な社会人基礎力を明確にする
まずは12の能力要素の中から、今の自社や部署、あるいは各個人にとって特に重要なものを3つほどピックアップし、1年かけて育成するなど、計画的に進めましょう。
2. 具体的な教育方法と環境を整える
「どのように身につけるか」という計画を立て、実践とフィードバックのサイクルを回していくことが、円滑な教育の鍵となります。
社会人基礎力は、働くすべての人の土台となる重要な能力です。ぜひ、若手社員のうちからしっかりと身につけられるよう、組織全体で育成に取り組んでいきましょう。
執筆者プロフィール
 新人育成トレーナー
新人育成トレーナー
アイキャリア株式会社太田 章代- 企業・団体でのコミュニケーション研修、ビジネスマナー研修など、2,000回以上(2023年現在)登壇。 プロフィール詳細
新着記事
-
-
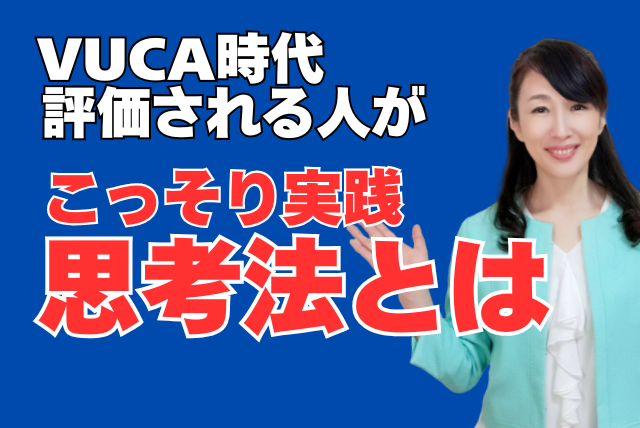
- 上司から「評価される人」と「されない人」の思考の決定的な違い 2025年10月20日
-
-
-
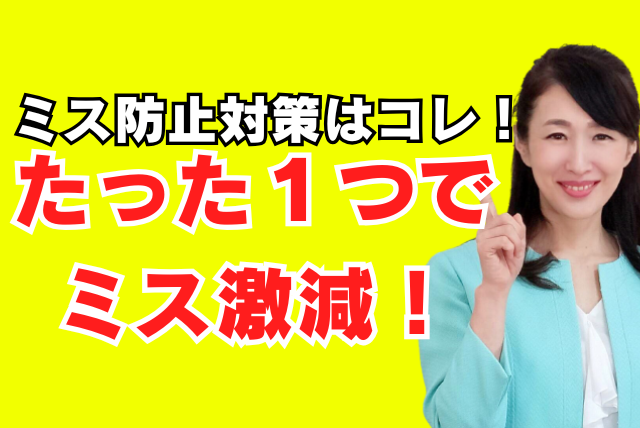
- たった1つでミス激減!ミス防止対策 2025年09月12日
-
-
-
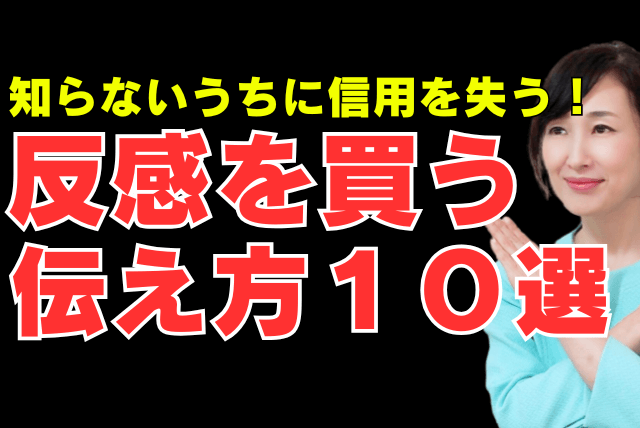
- 職場で反感を買うフレーズ10選|アサーティブコミュニケーションで好印象に! 2025年09月09日
-
カテゴリー