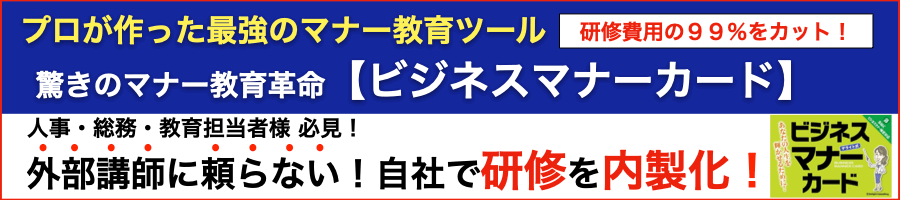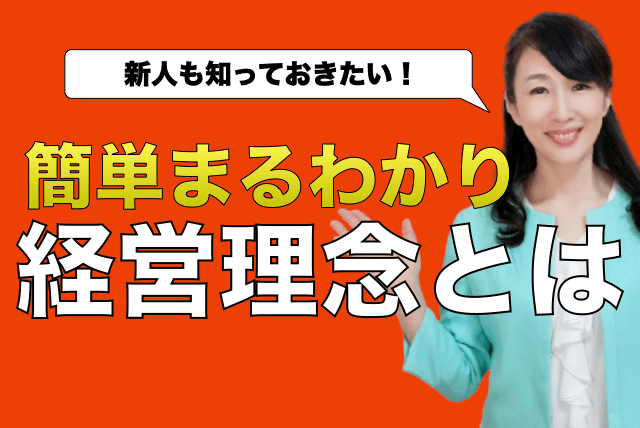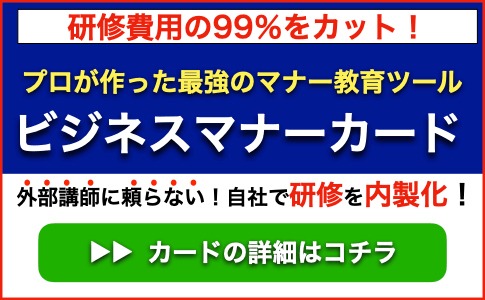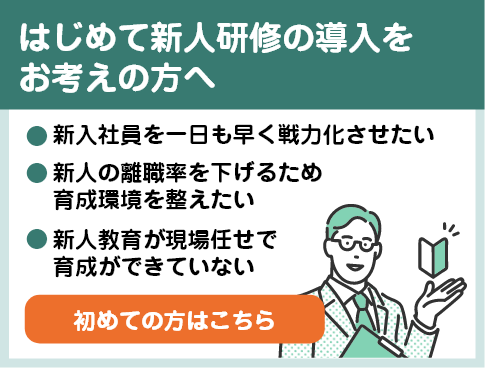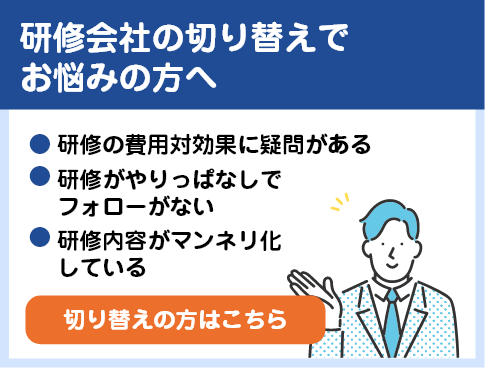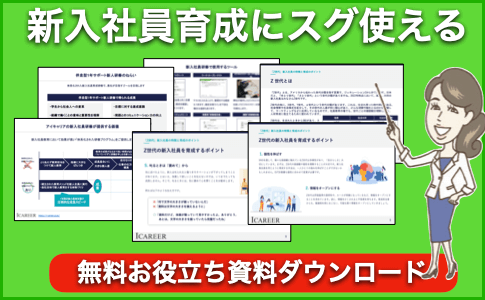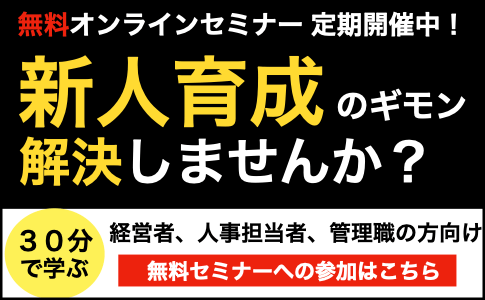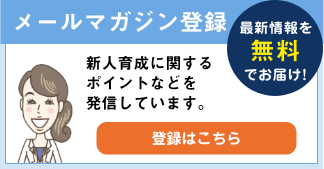新人が成果を出すのはどっち?「否定表現」と「肯定表現」
2024年06月19日 2024年06月22日 新人育成担当者向け
新入社員育成専門の研修トレーナー太田章代です。
突然ですが、あなたは相手から言われた言葉に不快感を覚えたことはありますか。
先日通っているホットヨガで何だか嫌な気持ちになったことがありました。考えてみるとヨガの先生が「否定表現」を使った指導をしていたことに気づいたのです。
ヨガの先生に悪気はないと思います。悪気がないからこそ、自分では気づかないものです。ここでは部下育成で気をつけたい「否定表現」「肯定表現」について詳しく解説します。
YouTube版も公開しています
動画でも学べます。聞き流すだけでも理解できますよ!
「否定表現」と「肯定表現」の特徴と受け取られ方
否定表現とは、「~ない」「~ません」と否定の言葉が入る表現です。それに対して肯定表現は、「~ます」と肯定で終わる表現です。
冒頭で触れましたが、ヨガの先生の否定表現はこんな感じでした。
否定表現「お腹に力を入れないと効果がありません。」
→否定表現は聞き手を注意している、威圧的、命令調と受け取られがちです(私は体験しました)
これを肯定表現にしてみます。
肯定表現「お腹に力を入れると効果が出ます。」
→肯定表現は聞き手を尊重している、前向きな表現で、受け入れやすい言葉です。
伝えたいことが同じでも、表現の仕方が変わるだけで聞き手の受け取り方が違ってきます。
新人指導には「肯定表現」が有効
仕事で部下へ指示を出すときや、アドバイスをするときには、良好な人間関係を築き成果を出してもらうためにも「肯定表現」を使うことをおすすめします。例えば、部下が一生懸命つくった企画書を上司に提出したときに以下のように言われたらどのように感じるでしょうか。
否定表現「要点がまとまっていないので、何が言いたいのかわかりません。」
このように言われたら、部下は頑張って企画書をつくったのにモチベーションがダダ下がりでしょう。また不安やストレスを感じてしまうこともあります。普段から否定表現が多い人は部下から知らないうちに嫌われているかもしれませんよ。同じことを伝えるにも肯定表現にすると以下の通りです。
肯定表現「要点をまとめると、言いたいことが伝わりますよ。」
このように伝えられれば、聞き手も「ありがとうございます」と受け入れることができ、前向きに企画書の修正に取り組めると思います。指示やアドバイスの目的は部下に成果をあげてもらうことです。
上司は部下のモチベーションを下げないように、肯定表現を選んで伝える意識が必要です。また肯定表現でアドバイスをすれば、言葉の意図が伝わりやすくなるというメリットもあります。
「否定表現」が有効な場合
ここまで「肯定表現」を使いましょうと伝えてきましたが、時と場合によっては「否定表現」の方が有効なケースもあります。否定表現は不安や恐怖心を植えつけるので、危険なことや強く言わなければならないことには最適な表現です。例えば以下のような場合です。
否定表現「危険ですのでロープの内側で作業をしない!」
肯定表現「危険ですのでロープの外側で作業をしましょう!」
→優しい肯定表現よりも、強い否定表現で危険なことを印象づけます。
否定表現「できる人は絶対にやらない習慣」
肯定表現「できる人がやっている習慣」
→これがYouTubeの題名なら、どちらを視聴したいですか。否定表現の方が押し出しが強くて興味がわくかもしれませんね。
状況に応じて表現を選んで伝えることができるといいのですが、普段の部下とのコミュニケーションでは「肯定表現」を使うことをおすすめします。
職場での「否定表現」を「肯定表現」に言い換えた例
では具体的に職場で部下の指導やアドバイスのときに使っている「否定表現」を、部下が受け取りやすい「肯定表現」に言い換えた例をみていきましょう。
否定表現「このやり方では、上手くいかないよ」
肯定表現「やり方を変えれば、上手くいくよ」
否定表現「計画性がないと、締切に間に合わないよ」
肯定表現「計画性があると、締切に間に合うよ」
否定表現「明日までに完成させてくれないと困るよ」
肯定表現「明日までに完成させてくれると助かるよ」
否定表現「報告が遅いと、仕事がスムーズに進みません」
肯定表現「報告が早いと、仕事がスムーズ進みます」
否定表現「挨拶の声が小さいと、お客様に悪い印象を与えるよ」
肯定表現「挨拶の声が大きいと、お客様に好印象を与えるよ」
まとめ
無意識に「否定表現」を使っている人は少なくありません。まずは日頃部下と接するときにどのような言葉を使っているのかチェックしてみてくださいね。「肯定表現」を習慣化して部下との関係性を良くし、働きやすい環境をつくっていきましょう。
執筆者プロフィール
 新人育成トレーナー
新人育成トレーナー
アイキャリア株式会社太田 章代- 企業・団体でのコミュニケーション研修、ビジネスマナー研修など、2,000回以上(2023年現在)登壇。 プロフィール詳細
新着記事
-
-
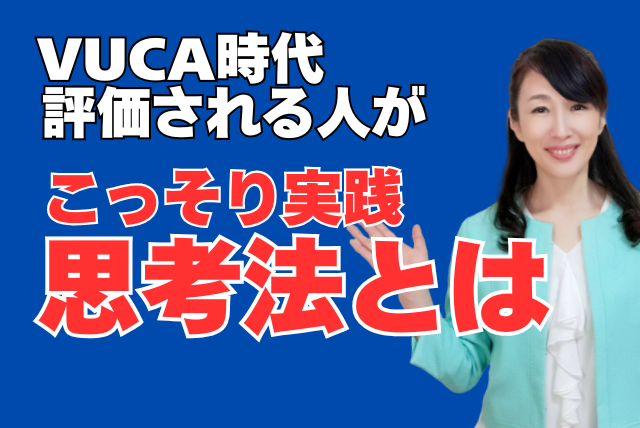
- 上司から「評価される人」と「されない人」の思考の決定的な違い 2025年10月20日
-
-
-
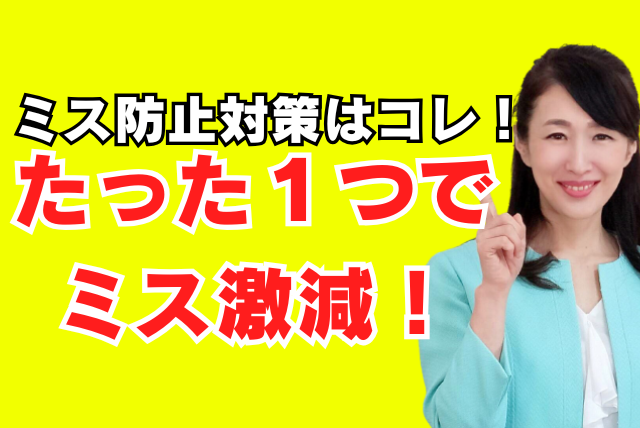
- たった1つでミス激減!ミス防止対策 2025年09月12日
-
-
-
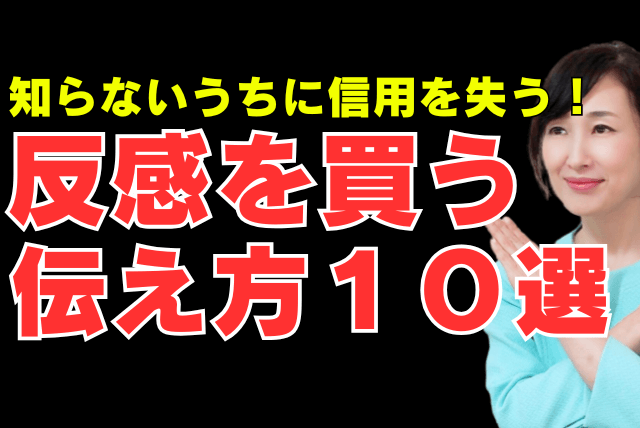
- 職場で反感を買うフレーズ10選|アサーティブコミュニケーションで好印象に! 2025年09月09日
-
カテゴリー