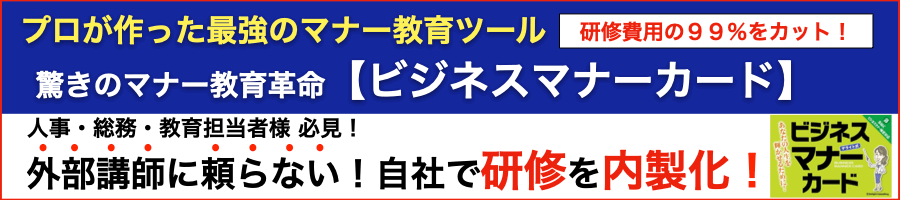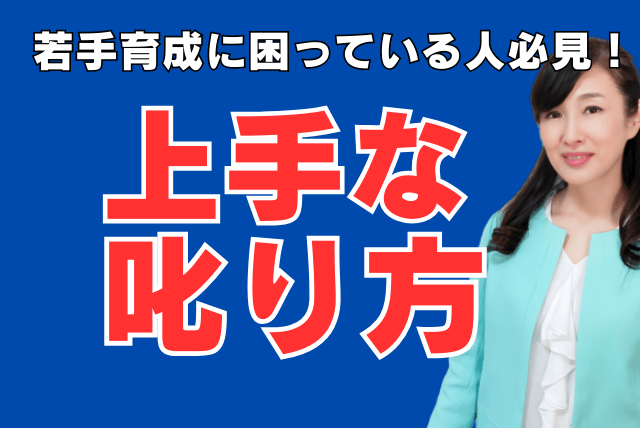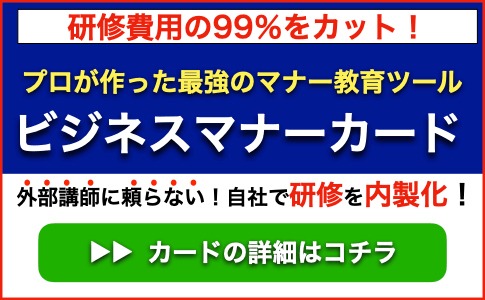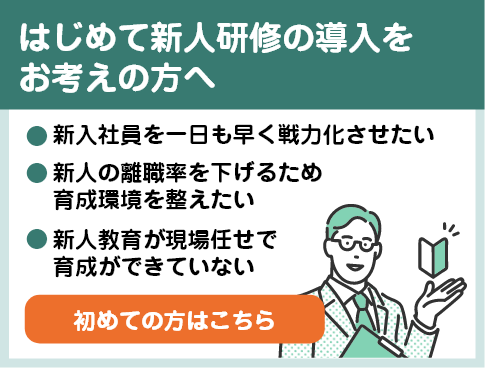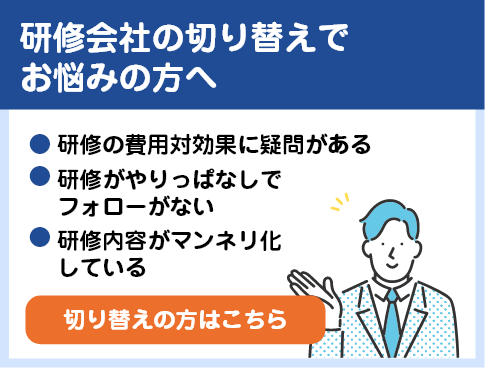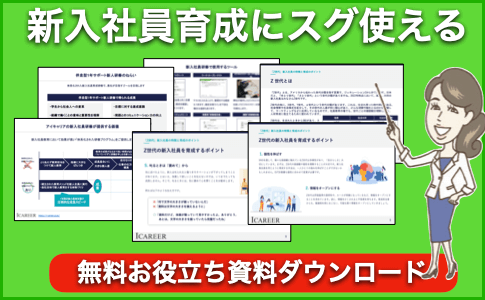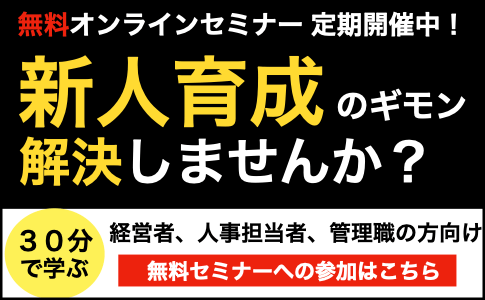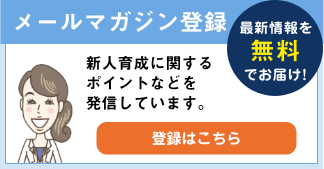上司から「評価される人」と「されない人」の思考の決定的な違い
2025年10月20日 2025年10月20日 新人育成担当者向け、ビジネスコミュニケーション
こんにちは、人材育成トレーナーの太田章代です。
上司から「評価される人と、されない人の思考」をご紹介します。
評価される人の思考は、VUCA(ブーカ)の時代を生きるために、絶対と言っていいほど必要なスキルです。
では、まず「VUCA」とは何か。
部下が伸びてブーカになったわけではありません(笑)
VUCAはとは、変化が激しく、将来が予測しにくい時代のことを言います。
当然、「評価される思考」があれば上司や会社から評価され、出世や昇進にもつながりますし、人間関係も円滑になります。
ここでは、以下の3つをご紹介します。
1. 評価されない人の思考 2パターン
2. 評価される人の思考
3. その具体例
YouTube版も公開しています
動画でも学べます。聞き流すだけでも理解できますよ!
上司から「評価されない人」の思考 2パターン
パターン 1:否定的思考
「否定的思考」があると、上司から何から仕事の依頼をされたときに「いや、それ無理ですね」「できないですよ」と、感情的に切り捨ててしまいます。
例えば、営業部の部長が売上を伸ばしたくて「営業エリアを広げよう!」と会議で言いました。否定的思考のある人は、間髪入れずに「営業エリアを広げても、売上は上がらないと思いますよ」と発言してしまいます。
エリアを広げても売上が上がらないというのは、データに基づいた本当の事実なのか、もしくは主観なのか。
といったら、何の根拠もない主観の可能性が高いものです。ネガティブな意見をみんなの前で堂々と言ってしまうと、チームに悪い影響力を及ぼしてしまいます。
人の意見を否定するときは、正確なデータに基づいた根拠と、代替案を伝えてください。例えば、エリアを拡大しても売上が上がらないと思うのなら、「私は、〇〇をしたら売上げが上がると思います」といったように自分の意見を伝えます。
否定的思考の方は「非協力的だ」と見なされてしまいます。
パターン 2:無批判的思考
「批判をしないならいいんじゃないか」と思いがちですが、実はそうではありません。これは、上司から言われたことに対して「分かりました」と何も考えずに受け入れてしまう“無批判的思考”の状態です。
たとえば、営業部の部長が「営業エリアを広げる」と言ったときに、「分かりました。来月から広げます」と、理由も背景も考えずに従ってしまうようなケースです。
一見「素直」とも言えますが、求められているのは“素直なイエスマン”ではありません。
無批判的思考に陥ると、
・自分の判断がない
・相手の言う通りに動くだけ
という受け身の姿勢になってしまいます。
新人のうちはそれでも仕方ない部分がありますが、経験や知識を積んでも“何も考えないまま従う”のは危険です。
変化の激しいVUCAの時代に必要なのは、「言われたことをこなす力」ではなく、「自分で考えて行動する主体性」です。言いなりで動くだけでは、「何も考えていない人だな」と評価されてしまいます。
上司から「評価される人」の思考:批判的思考(クリティカルシンキング)
では次に、評価される人の思考「批判的思考(クリティカルシンキング)」についてお話しします。この思考は、ぜひ皆さんに身につけていただきたい重要な力です。
「批判的」と聞くと、相手を否定したり責めたりするようなイメージを持たれるかもしれません。しかし、ここでいう批判的思考とはそういう意味ではありません。
批判的思考とは、「本当にこれでいいのか?」と疑問を持ち、自分の頭で考える力のことです。
例えば、営業部の部長が「営業エリアを広げるぞ」と言ったとき、「はい、分かりました」と何も考えずに受け入れるのでもなく、「それはダメです」と感情的に否定するのでもなく、「営業エリアを広げる必要はなぜあるのか?」と自分の中で問いを立てて考えるのです。
批判的思考がある人は、次のような特徴があります。
・物事を客観的に分析できる(営業エリアを広げたら売上はどう変わるのか)
・問題点を見つけ、改善策を考えられる
・事実やデータに基づいて論理的に検証できる
このように、批判的に考えることで、感情や思い込みに流されず、より良い判断や意思決定ができるようになります。だからこそ、批判的思考は今の時代に「評価される人の考え方」なのです。
なぜ批判的思考が必要なのか?
VUCAの時代、つまり変化が激しく将来の予測が難しい時代に私たちは生きています。本当に、時代の流れが劇的に早くなっていますよね。
これまでの時代では、「経験」や「知識」で多くの問題を解決することができました。しかし今は、経験したことのない問題が次々に起きています。
例えば
1.AIの急速な進化
仕事のどの部分をAIに任せ、どこを人が担うべきか、判断が求められるようになりました。これは、誰もが初めて経験する課題です。
2.価値観の多様化
世代や働き方の違いが広がり、人材マネジメントの在り方も大きく変わっています。かつての育成スタイルをそのまま続けてしまうと、今の部下には合わず、モチベーション低下や離職につながることもあります。
だからこそ、特にベテランの方や経験豊富な方ほど、「自分の経験や知識を一度“疑う」。つまり批判的思考で考えることが大切です。
心理学では、「自分の意見は正しい」「これはこういうものだ」と決めつけてしまう思考のクセが誰にでもあると言われています。私自身もそうですが、つい“過去の成功体験”で判断してしまうことがあります。
しかし、これからの時代に必要なのは、ゼロベースで考える習慣です。「本当に今もそれが正しいのか?」「他の方法はないか?」と、自分の考えを一度立ち止まって見直してみる。それが、変化に強い人・成長し続ける人の思考法なのです。
批判的思考(クリティカルシンキング)の具体例
例 1:洋服のバーゲン企画
例えば、ファッション関係の会社では、「バーゲンは毎年7月と12月に開催する」と決まっているとします。長年続けてきた慣習なので、誰も疑わず「そういうもの」と思っているケースです。
でも、ここで批判的思考を働かせてみましょう。
・そもそも、バーゲンは本当にやる必要があるのか?
・7月と12月という時期設定は、今の時代に合っているのか?
・温暖化の影響で季節の感覚が変化している中、夏服・冬服の売上ピークは実際いつなのか?(データを確認してみる)
・お客様は本当に7月と12月のバーゲンに満足しているのか?
こうした問いを立てて、データや顧客の声をもとに検証する。これこそが「批判的思考」です。
つまり、「今までそうだったから」「みんながそうしているから」ではなく、“今の時代に合っているか”を自分の頭で考えること。その積み重ねが、変化の激しいVUCAの時代における“成長する組織”をつくる力になります。
例 2:1on1ミーティングの導入
最近、上司と部下のコミュニケーションがうまくいっていないため、「1on1を月1回行おう」と検討するのは自然な発想です。しかし、自分の意見にも批判的な視点を入れて点検することが重要です。
・本当に1on1は必要なのか?
・月1回という頻度で、期待する目的(信頼構築や課題把握)は達成できるのか?
・1on1を導入したとき、部下はどのように受け止めるのか(負担に感じるのか、効果に期待するか、本音が出るか)
これらの問いを立てて、目的・頻度・形式を部下の声やデータで検証していきましょう。
まとめ
ここまで、上司から評価される人と、評価されにくい人の思考の違いを見てきました。
「否定的思考」や「無批判的思考」は評価につながりません。これからのビジネスパーソンに求められるのは、「批判的思考=自分の頭で考える力」です。
仕事に取りかかるときは、常に「本当にこれでいいのか?」と問いかけ、物事を多角的に捉えることで、より良い判断と成果につなげていきましょう。
執筆者プロフィール
 新人育成トレーナー
新人育成トレーナー
アイキャリア株式会社太田 章代- 企業・団体でのコミュニケーション研修、ビジネスマナー研修など、2,000回以上(2023年現在)登壇。 プロフィール詳細
新着記事
-
-
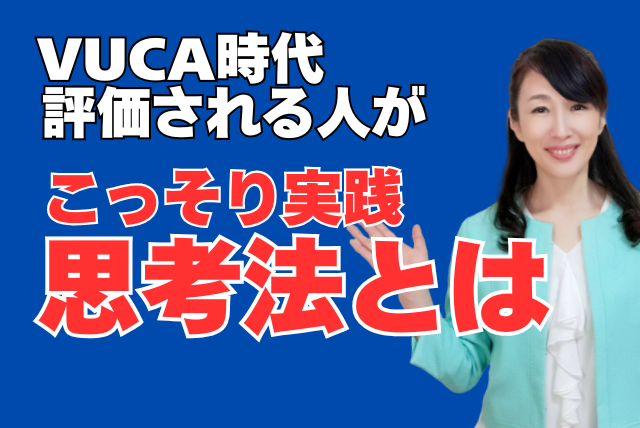
- 上司から「評価される人」と「されない人」の思考の決定的な違い 2025年10月20日
-
-
-
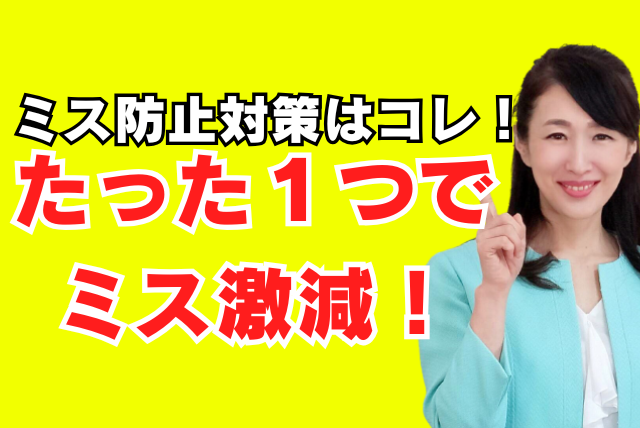
- たった1つでミス激減!ミス防止対策 2025年09月12日
-
-
-
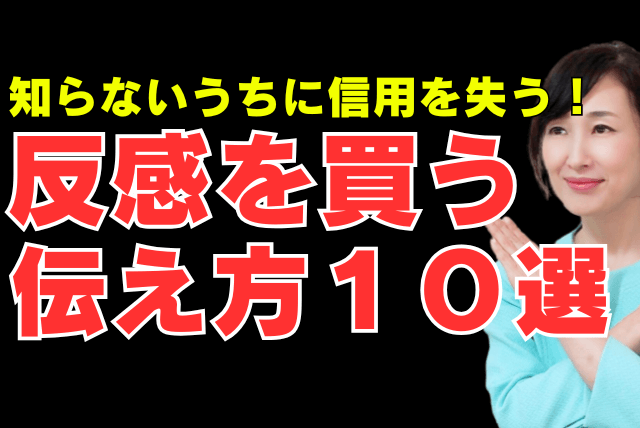
- 職場で反感を買うフレーズ10選|アサーティブコミュニケーションで好印象に! 2025年09月09日
-
カテゴリー